サインボード 2 部品説明 |
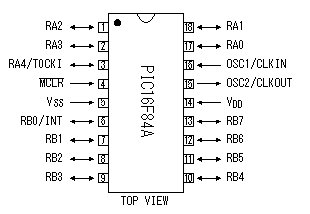 PIC16F84Aを使用しています。PIC16F84Aは発振器として20MHzまで使えますが、今回は高速動作は必要ないので、10MHzのレゾネータを使用しています。もっと低い周波数でも問題はありませんが、タイマー処理の時間に関係するので、今回、私が紹介するソフトを使用する場合には10MHzの発振器を使う必要があります。  LEDのラッチレジスタ機能を持たせています。 112個のLEDのラッチを行うので、1つではピン数が足りず、2個使用しています。 このCPLDのロジックについては「電子掲示板用 7ビット x 16列 ラッチレジスタ」を参照して下さい。  サインボードの表示部周囲に取り付けた飾り用のLED(緑)の表示を移動させるために5進のカウンターを使用しています。 このCPLDのロジックについては「電子掲示板用 5ビット カウンター」を参照して下さい。 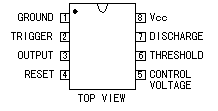 5進カウンターを動作させるためのクロックパルスを発生させます。 555にはセカンドソース(互換品)が沢山ありますが、発振波形が微妙に違う場合があります。 私の経験では、NE555を使用したときにきれいな矩形波で発振せず、カウンターが誤動作したことがあります。 今回はCMOSタイプのTLC555を使用しました。 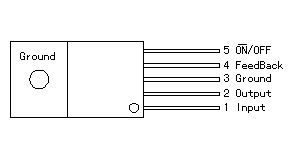 7Vから40Vまでの入力電圧を+5Vの安定した電圧にするスイッチングレギュレータです。 1Aタイプです。  PICのソフトウェアは必要に応じて変えるので、取り外せるようにICソケットを使用します。 TLC555は取り外すことはないので、プリント基板に直接取り付けてもOKです。  CPLDを搭載するためのソケットです。 84ピンタイプと44ピンタイプを使っています。  スイッチングレギュレータの内部損出は少ないので、大きな放熱器を付ける必要はありません。 今回の場合、最大1W位の損出が出ます。小型の放熱器を取り付けました。  10MHzのレゾネータを使用しています。発振用のセラミック発振子とコンデンサが内部で組み合わされています。  データ表示部には赤色の高輝度タイプのLEDを使用しています。 表示部の周囲には緑色のLEDを取り付けました。 いずれのLEDも透明タイプで5mm径のものです。  表示部のLEDの電流を制御するための抵抗器です。 組立が容易なので、抵抗アレーを使用しました。 一つの抵抗器アレーには4つの独立した抵抗器が入っています。  周囲の飾り用LEDの電流制御用に1/8Wの抵抗器を使用しました。 5個づつ5組使うので、抵抗アレーではなく、通常の抵抗器を使用しました。  周囲の飾り用LEDの点灯移動速度を設定するために使用しています。 頻繁に変更するわけではないので、半固定タイプを使用しています。  スイッチングレギュレータ用のコイルです。 トロイダルコイルの概要はトロイダル・コイルを参照して下さい。  スイッチングレギュレータで使用するダイオードです。 今回使用しているLM2575ではスイッチング周波数が約52KHzです。通常のダイオードでは逆回復時間が長いので使えません。 ショットキーバリア・ダイオードの概要についてはショットキー・バリア・ダイオードを参照して下さい。  555発振器およびスイッチングレギュレータには電解コンデンサを使用しています。 スイッチングレギュレータ出力の平滑コンデンサには等価直列抵抗値(ESR:Equivalent Series Resistance)の少ないものを使用します。コンデンサの特性を解析すると、コンデンサの性質以外に、コイルおよび抵抗の性質を持っています。この抵抗値を等価直列抵抗値(ESR)と言います。ESRの値が大きいとコンデンサに電流が流れた場合、電力損失が大きくなり、発熱することになります。 スイッチング・レギュレータの平滑回路で使用するコンデンサには大きな電流が流れますので、ESRの大きいコンデンサでは発熱してしまいます。  40×55ホールのユニバーサル基板を使用しています。  電源線を接続するための端子として使用しています。  今回の装置ではLED表示部と制御部を別のプリント基板で作りました。 2枚のプリント基板は背面同士を向かい合わせて取り付けています。プリント基板同士のスペーサとして10mmのスタッドを使用しています。  このスタッドは装置をアクリル板へ取り付けるために使用しています。 長さ10mmのものを使用しました。  AC100VからDC12VにするためのACアダプタです。 スイッチングレギュレータを内蔵したタイプで出力は1Aまで流すことができます。 秋月電子通商で購入したもので、2000年7月時点で850円でした。  ACアダプタを接続するためのコネクタです。 コネクタのピンサイズは何種類かありますので、アダプタのプラグに適合したコネクタを使う必要があります。今回使用したコネクタは「2.1」と言うものです。  今回の装置はアクリル製の簡単なカバーを付けてほこり避けをしました。  LEDはユニバーサル基板に取り付けていますが、そのままでは見栄えが悪いので、基板に黒い紙を付け、その上からLEDを取り付けました。LEDの穴を開けるのには基板と紙を四隅で固定し、発砲スチロールの上に置いて基板の裏から細いピンを差し込んで穴を開けました。162個のLEDなので324個の穴をあけることになります。結構大変です。 |